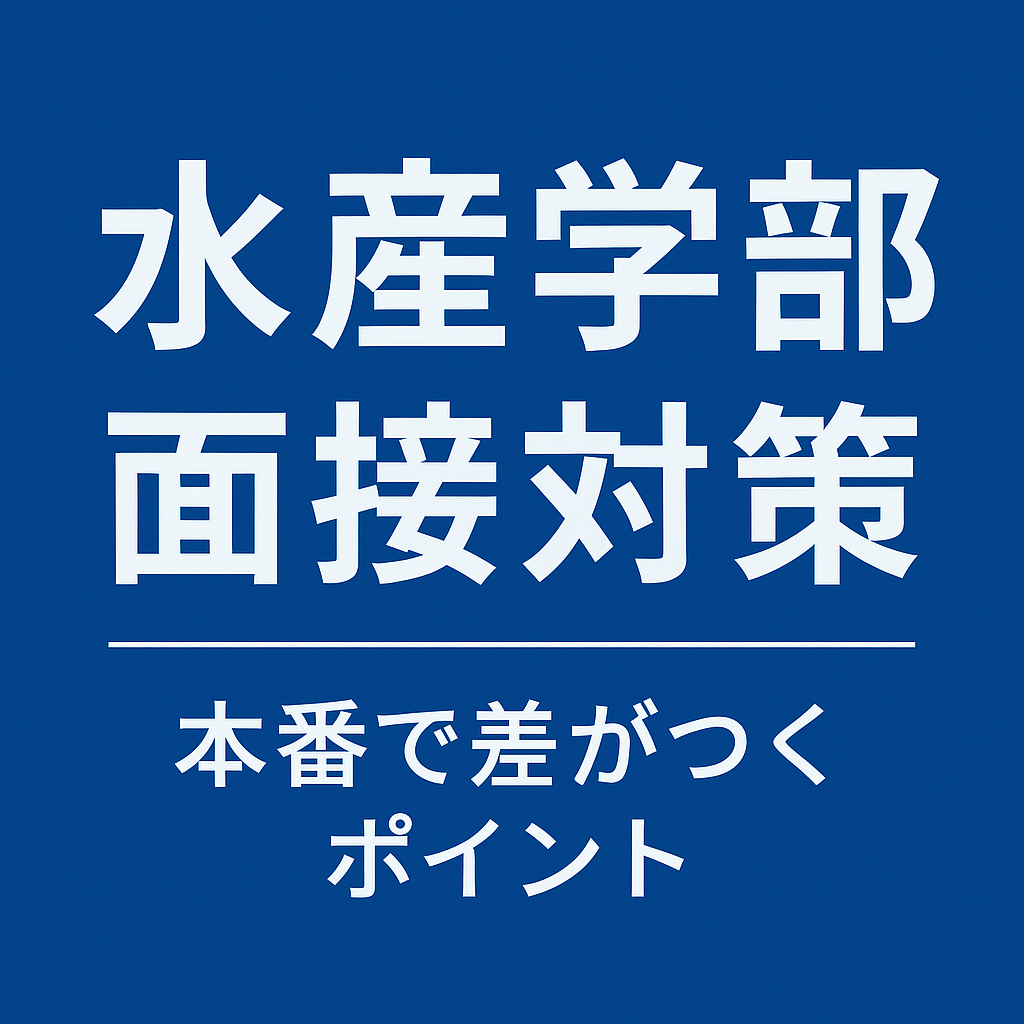水産学部を志望する理由を明確にしよう
はじめに:水産学部の面接は“志望動機の深さ”がカギ
水産学部の面接は、他学部と比べてやや専門性が求められる傾向があります。水産業の未来や海洋資源の保全、水産バイオテクノロジー、地域漁業の振興、食品安全など、社会との関わりが強い分野を扱うため、**「なぜ水産学部を志望するのか」**という問いに対する明確な答えが非常に重視されます。
加えて、漠然と「海が好き」「魚が好き」といった回答では不十分であり、その背景にある経験や学びたい内容、将来の展望まで踏み込んだ受け答えが必要です。
面接対策の第一歩として不可欠な「志望動機」の深掘り方法や、評価されやすい志望理由の構成法を解説していきます。
なぜ「水産学部なのか」を自分の言葉で語れるようにする
面接では「なぜ水産学部を選んだのですか?」という質問は必ずと言っていいほど出されます。この質問に答えるためには、以下の3つの視点を意識して準備しましょう。
① 過去の体験から導かれた「原体験」
水産学部を志望する動機として説得力があるのは、個人的な原体験に基づいた話です。以下のようなエピソードがあると強い印象を残すことができます。
-
小学生の時、漁港で見た養殖場に感動し、水産業に興味を持った
-
家族が漁業関係の仕事をしており、身近に課題を感じていた
-
地元で開催された「海とさかなの体験教室」でマグロの解体を見て感動した
-
中学生の自由研究で海洋ごみの調査を行い、水産資源の危機に関心を持った
▶︎ ポイント:体験→関心→学びたいことの流れを意識すると、構成が自然になります。
② 水産学部で学びたいことを具体的に
単に「海に関することを学びたい」では弱い印象になります。具体的なキーワードを入れることが重要です。
例:
-
「海洋資源の持続的利用について研究したい」
-
「養殖技術の改良を学び、地元の漁業を支えたい」
-
「海洋バイオテクノロジーに興味があり、医療や環境保全に役立てたい」
▶︎ 大学のカリキュラムや研究室紹介ページを事前に調べ、「この大学だからこそ学べること」を把握しておくと好印象です。
③ 将来の目標・貢献意識
水産学部の面接では、社会貢献や将来像に関する質問も多く出ます。「水産学を学んだあと、どう社会に役立てたいのか?」という視点を持ちましょう。
例:
-
「将来は地元の漁協で働き、地域ブランド魚の普及に携わりたい」
-
「水産加工業に就職し、日本の魚食文化を守りたい」
-
「国際機関で水産資源管理に関わる仕事がしたい」
▶︎ ポイント:**「自分が得た知識や技術を、誰にどう活かすのか」**という構想まで話せると説得力が増します。
志望理由の構成テンプレート(面接でそのまま使える)
以下は、面接本番での発話に適した構成例です。
【例文構成】
-
原体験:「私は小学生のときに訪れた水族館で、海洋生物の多様性に感動しました。」
-
興味の深化:「その後もテレビ番組や本などで海の生態系について学ぶうちに、水産業が直面する環境問題にも関心を持つようになりました。」
-
志望理由:「貴学の水産学部では、持続可能な海洋資源の利用に関する研究が盛んであり、私の興味と合致しています。」
-
将来の目標:「将来的には海洋環境の保全に関わる研究者になりたいと考えています。」
志望動機で避けたいNGパターン
-
「なんとなく理系っぽいから」「他に興味がある学部がなかった」
-
「水族館が好きだから」「魚を食べるのが好きだから」→背景や発展性がない
-
「将来のことはまだ何も考えていない」→正直でも評価されにくい
▶︎ 面接では、自分の進路に責任を持っていることが信頼につながります。
頻出質問と答え方のコツ ― 面接本番で差をつけるために
水産学部の面接では、「志望動機」に加え、本人の人間性や将来への姿勢、課題意識を測る質問が多く見られます。単に知識を問う試験ではなく、大学で主体的に学ぶ意欲とビジョンがあるかを見極められるため、事前に「型」を用意しておくことが大切です。
このパートでは、面接で頻出する質問とその答え方のポイントをテーマ別に整理し、模範的な回答例も紹介します。
1. 志望理由に関連した深掘り質問
これは第1パートの延長線ですが、面接官は志望理由を聞いた後にさらに掘り下げてくることが多くあります。
よくある質問例:
-
「なぜ水産学部でなければならないのですか?」
-
「環境学部や農学部ではダメな理由はありますか?」
-
「高校で取り組んできたこととどうつながっていますか?」
回答のコツ:
-
他学部との違いを理解しておく。
-
水産学部特有の学問領域(例:漁業経済学、養殖技術、魚類生理学など)を答えに盛り込む。
-
自分の関心領域と大学のカリキュラム・研究テーマを結びつけると効果的。
回答例:
「水産学部では、海洋生物や漁業経済の分野まで一貫して学べる点に魅力を感じました。私は高校でSDGsの学習をした際に、海洋資源の持続的な利用という課題に深く関心を持ちました。貴学では、養殖技術や水産バイオテクノロジーに関する講義が充実しているため、自分の興味に直結した学びが得られると考えています。」
2. 高校生活に関する質問
大学は、知識だけでなく主体性・協調性・継続力を重視します。高校時代の部活動、探究活動、生徒会活動、アルバイト経験なども質問されることが多いです。
よくある質問例:
-
「高校時代に力を入れたことは何ですか?」
-
「その経験から学んだことはありますか?」
-
「つらかったことはどう乗り越えましたか?」
回答のコツ:
-
エピソードを「課題→行動→結果→学び」の順で構成する。
-
一見水産学部と関係なさそうな体験でも、「学び」や「気づき」を通して志望と関連付ける。
回答例:
「私は水泳部に所属しており、体力面だけでなくチームで練習を支え合う重要性を学びました。特に、自分よりタイムが遅い後輩の練習に付き添い、一緒に泳ぐことでモチベーションを高めてもらえた経験は、人を支える喜びを知るきっかけになりました。こうした経験は、将来水産業に携わり、地域の人々と連携して働く際にも活かせると感じています。」
3. 社会的な課題に対する関心
水産業は現在、資源の減少、海洋ごみ問題、漁業従事者の高齢化など多くの社会的課題と直面しています。こうした話題に対して、自分なりの考えを持っているかどうかも問われます。
よくある質問例:
-
「現在、水産業が抱える課題にはどのようなものがありますか?」
-
「それに対してあなたが大学で学びたいことは何ですか?」
-
「将来、どのようにその問題に貢献したいですか?」
回答のコツ:
-
ニュースや新聞、SDGs関連の情報から事前に情報収集しておく。
-
課題→自分の問題意識→学びの方向性→将来像、という流れで構成する。
-
大きな話でなくても、自分なりに考えている姿勢が大事。
回答例:
「近年、海洋プラスチック問題が深刻化しており、特にマイクロプラスチックが魚の体内に蓄積されている事例に危機感を抱きました。水産物の安全性だけでなく、食文化の継承にも関わる問題だと感じています。私は大学で水質や環境科学について学び、地域レベルでできる環境保全活動にも取り組みたいと考えています。」
4. 学部での学びや進路に関する質問
面接官は「大学に入ってから何をしたいか」「卒業後に何を目指すか」という点にも注目します。あくまで予定でもよいので、未来への構想力を見せることが重要です。
よくある質問例:
-
「入学後に取り組みたい研究や分野はありますか?」
-
「将来の夢や目標を教えてください」
-
「水産学部で学んだことをどのように活かしたいですか?」
回答のコツ:
-
具体的な講義名や教授名、研究分野に言及すると好印象。
-
「まだ決めていない」という場合も、興味ある分野を1つ挙げるようにする。
回答例:
「水産加工や保存技術に関心があり、特に低温保存や冷凍技術の分野に興味があります。貴学では食品工学の研究室があると知り、そのような専門性の高い環境で技術と科学の両方を学びたいと考えています。将来的には、安全でおいしい水産物を世界中に届ける仕事に携わりたいです。」
本番で差がつく!面接マナーと実践テクニック
面接対策において、志望動機や回答の準備だけで満足してしまってはいけません。水産学部の面接では、話す内容以上に「どんな態度で」「どんな印象を与えるか」も重視されます。
当日の身だしなみや姿勢、受け答えの姿勢、緊張対策の方法、そして模擬面接の活用術まで、本番で実力を発揮するための実践的なポイントを紹介します。
1. 第一印象で好感を得る服装と態度
面接における第一印象は、想像以上に合否に影響します。見た目や態度が整っていることで、「きちんと準備している学生だ」「社会性がある」と判断されることがあります。
【服装・髪型】
-
男子:無地のシャツにジャケット、黒または紺のスラックス。髪型は短めで清潔感を意識。ネクタイは任意。
-
女子:シンプルなブラウスにジャケットまたはカーディガン。スカートでもパンツでもOK。ナチュラルメイク推奨。
-
共通:派手すぎる色・柄は避け、靴は磨いておく。香水・アクセサリーは控えめに。
【入室時の基本マナー】
-
ドアをノックして「失礼します」と言い、面接官の「どうぞ」後に入室。
-
ドアを静かに閉め、椅子の横で「○○高校から参りました△△△△です。本日はよろしくお願いします」と丁寧に挨拶。
-
座る際は「失礼いたします」と一言添える。
▶ポイント:緊張していても、「ゆっくり・丁寧に・落ち着いた動作」を心がけましょう。
2. 声・表情・姿勢で“非言語の好印象”をつくる
面接で大切なのは「言葉」だけではありません。実際、印象の7割以上が「非言語情報(態度・表情・姿勢・声のトーンなど)」によって形成されるといわれています。
【声のトーン・話し方】
-
声はやや高め・はっきりと。
-
「えーと」「あのー」などのつなぎ言葉は避ける。
-
重要なところでは語尾を下げて自信ある印象を。
【目線】
-
面接官の目元を見る意識を持つ(目線を泳がせない)。
-
書類や机を見下ろしすぎない。
【表情】
-
笑顔を忘れず、特に冒頭と締めの挨拶では明るさを意識。
-
緊張していても、口角を少し上げるだけで印象は大きく変わります。
【姿勢】
-
背筋を伸ばし、座面の半分ほどに浅く腰掛ける。
-
手は膝の上で組む、もしくは自然に重ねる。
-
身体を揺らさず、余計な動作は控える。
▶これらの要素を日常的に意識して練習しておくと、本番でも自然に表現できるようになります。
3. 緊張を味方に変える方法
面接本番では多かれ少なかれ緊張します。それ自体は悪いことではなく、「準備してきた証」として面接官も理解しています。大切なのは、緊張をどうコントロールするかです。
【緊張対策の具体例】
-
面接当日の朝、深呼吸を3回×3セット繰り返す。
-
「緊張している=真剣に取り組んでいる証」と肯定的に捉える。
-
質問が詰まったときは、「少し考えさせてください」と言って間を取る勇気を持つ。
-
目の前の面接官を「学校の先生だ」とイメージして自然体で話す。
▶「完璧な受け答え」よりも、「自分の言葉で丁寧に答えようとする姿勢」の方が評価されます。
4. 模擬面接は本番前の必須トレーニング
練習なしに本番で良いパフォーマンスを発揮するのは至難の業です。学校の先生や家族・友人を相手に模擬面接を繰り返すことで、内容の整理だけでなく「慣れ」も手に入ります。
【模擬面接で確認すべきポイント】
-
内容が面接時間内に収まるか(平均10〜15分)
-
回答が長すぎず、伝えたい要点が明確か
-
表情・声のトーン・姿勢に違和感はないか
-
質問に対して論理的な構成で答えられているか
-
「この大学・学部にどうしても行きたい」という熱意が伝わっているか
▶スマホで動画を撮って自己チェックをするのもおすすめです。
5. 面接終了後も気を抜かず、最後まで好印象を
面接の最後では、次のような質問で締めくくられることが多いです:
-
「最後に何か伝えておきたいことはありますか?」
-
「質問はありますか?」
この場面では、「感謝の気持ち」や「入学への意欲」を短くでも言葉にすると好印象です。
【例】
「面接のお時間をいただき、ありがとうございました。水産学の学びを深められる貴学にぜひ進学したいという気持ちが、さらに強まりました。」
▶そして、退室時には必ず一礼し、「ありがとうございました」と明るく言ってから退出しましょう。
まとめ
水産学部の面接は、知識だけではなく人柄・将来への姿勢・熱意・礼儀のすべてが評価される試験です。準備した内容を活かすためには、服装・態度・話し方などの「非言語コミュニケーション」への意識が欠かせません。
丁寧な準備と繰り返しの練習で、自信を持って面接本番に臨みましょう。
あなたの言葉と姿勢が、大学側にしっかりと伝わることを願っています。
日本経済大学 福岡キャンパスの オープンキャンパスに行ってみよう! 福岡・太宰府にある日本経済大学〈福岡キャンパス〉では、来校型とオンライン型のオープンキャンパスを定期的に開催しています。保護者の同伴も歓迎されており、大学の雰囲気や学びの内容を実際に体験できる絶好のチャンスです。 オープンキャンパスではこんな体験ができます: ・学科紹介や模擬授業で、大学での学びが具体的にわかる ・在学生との交流コーナーでリアルなキャンパスライフを聞ける ・キャンパスツアーで、太宰府の自然に囲まれた校舎を見学 ・参加特典の配布もあり(※内容は時期によって異なります) アクセスも便利! キャンパスは西鉄太宰府駅から徒歩約10分。博多駅や天神エリアからのアクセスも良好で、遠方からの参加もしやすい立地です。周辺には太宰府天満宮や九州国立博物館もあり、見学のついでに観光も楽しめます。 ▼オープンキャンパスの詳細・申込はこちらから: https://www.jue.ac.jp/juken/open_campus/ ▼福岡キャンパスへのアクセス情報はこちら: https://www.jue.ac.jp/access_fukuoka/