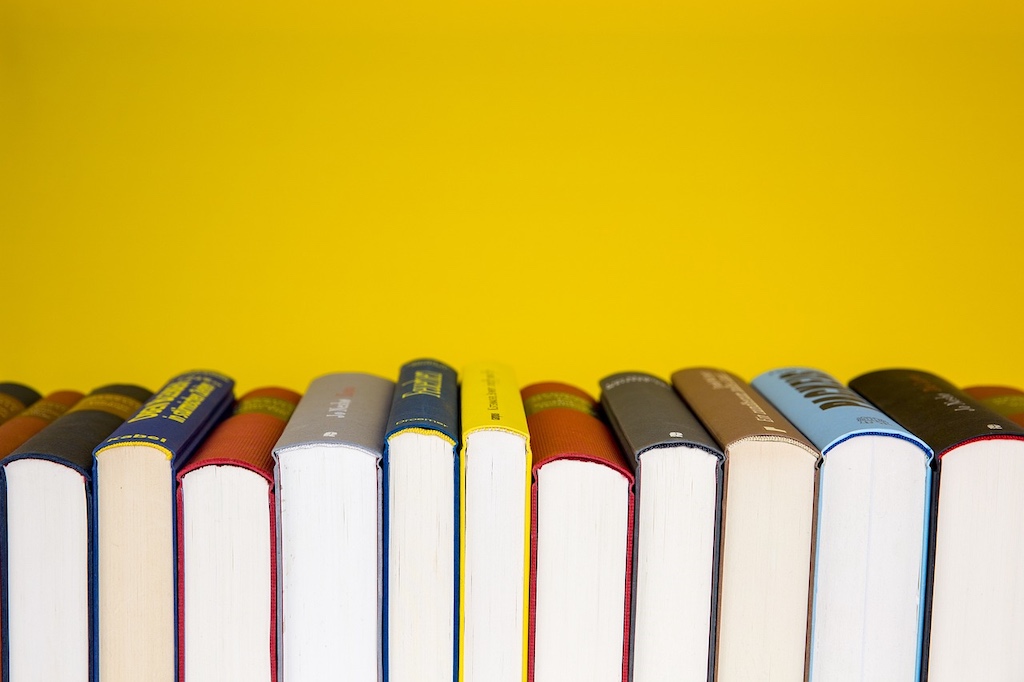経営学部では、大学の恵まれた環境のなかで、経営に関するあらゆる知識・スキルを学べるため、将来この学部で習得したことは、あらゆる業種において活用できます。
経営に関する仕事について調べていくと目に入るのが、経営コンサルタント・シンクタンクという言葉です。この2つは具体的にどのような内容なのか、関心を寄せている高校生の方々もいるでしょう。
今回は、経営コンサルタント・シンクタンクそれぞれの詳細、両者の違いなどについて、詳しく解説していきます。高校生のみなさんで興味のある方は、ぜひ参考にしてみてください。
経営コンサルタントとは
経営コンサルタントとは、企業の業績・経営の問題点を把握して、問題を解決するためのサポート・アドバイスを行ない、企業の業績・経営を円滑に進める役割を担う職種です。
その企業が抱えている悩みをしっかりとヒアリングして問題点を浮かび上がらせ、「何が原因なのか」「改善策は何か」「企業にとって最良の選択肢は何か」という点を、その企業の視点・社会的地位を考慮したうえで、提示・提案します。
企業の性格を見抜く分析力・その企業が所属する業界の市場動向・改善のために可能な資金・企業の体力など、総合的な分析・解析を行ない、アイデアの提供をするのが、経営コンサルタントの役割です。
このような業務を進めるためには、経営に関する豊富な知識・情報収集力・分析力がなくてはいけません。あくまで物事を客観視して、どのような策が最良なのかを、冷静に分析・発案するスキルも必要です。
また、コンサルティングだけでなく、講演・書籍執筆・メディア出演のコメンテーターなど、その業務内容は多岐にわたります。
シンクタンクとは
シンクタンクとは、経営・経済などあらゆる社会的問題に対して分析・研究を行ない、解決策の考案および提供・実践をする研究機関です。
シンクタンクは、国家・政府クラスの大規模なものもありますが、日本では、専門性の高い知識・スキルを駆使して企業が抱える問題をサポート・アドバイスをする役割という認識になっています。
経営コンサルタントはコンサルティング専門機関に所属、あるいは個人事務所での運営をしているのに対して、国内のシンクタンクは大手企業の子会社として運営されているケースが多いです。
経営コンサルタントのメリット・デメリット
一つの仕事としてみた場合、経営コンサルタントにはどのようなメリットがあるのでしょうか。以下よりメリット・デメリットを紹介しましょう。
メリット
経営コンサルタントのメリットの一つは、高収入が狙えるという点です。現在コンサルティング依頼をする企業は多く多大なニーズがあり、仕事に困ることはほぼないといってもいいでしょう。経営コンサルタントの平均年収は一般の相場よりやや高めです。あくまで平均なので頑張り次第で高収入も実現します。
また、業績不振の企業を改善した際の達成感も、経営コンサルタントの魅力です。昔ながらの中小企業は現在に対応した経営策を持っていないため、今の時代に見合った改善策を提供して業績が回復すれば、会社の社長だけでなく多くの従業員から多大な感謝をされるでしょう。
多くの人から感謝をされ、それが自分の実績にもなるため、メンタル面・収入面どちらも達成感・満足感を得られます。
デメリット
経営コンサルタントのデメリットは、仕事に忙殺される可能性があることです。コンサルティングを求めている企業は多いため、休む暇がないほど働くことになります。高収入を目指している人ならともかく私生活も重視したい人は苦しいかもしれません。また、多忙により健康を害する恐れもあるでしょう。
また、多様な知識・スキルを要求されることも、経営コンサルタントの苦しい面です。経営学だけでなくあらゆる市場の動きを把握する情報収集力・企業の現状を把握する観察力も必要となります。また、コミュニケーション能力も重要です。
シンクタンクのメリット・デメリット
シンクタンク業務のメリット・デメリットは、以下の通りです。
メリット
シンクタンクのメリットは大手企業の系列グループなので、安定感があることです。大手なので世間の市場動向に変化があっても大きな変化がなく、常に安定した生活を送れます。また、クライアントも大手企業・国家レベルであることが多いため、ハイレベルな人間との交流が可能です。
そして、大きな業務を完了させた時の達成感も、この業務の特徴です。自分が行なった仕事の成果が公的なデータとして扱われることもあるため、大きな満足感が得られるでしょう。
デメリット
シンクタンクのデメリットは、ハイレベルな環境に身を投じる点です。クライアントもシンクタンクには高額の依頼料金を支払っているため、高度な要求をしてきます。一般的な水準以上の成果を期待しているため、ハイレベルな能力が備わっていないと、この業務は継続できないでしょう。
また、平均以上の多様な知識・スキルを要求されるため、日頃からの知識・スキルのインプット・アウトプット・アップデートも行わないと、この業務はやっていけません。
シンクタンクへ所属するのは、ハイレベルな知識・スキルを取得することが必須です。そしてシンクタンク所属で業務を継続することも決して楽ではありません。
経営コンサルタントに向いている人
経営コンサルタントに向いている人は、以下のような特徴があります。
トラブル・想定外の出来事に対応できる人
経営コンサルタントは、企業の経営不振の改善サポート・アドバイスが主な業務です。経営コンサルタントのアドバイスで一時的に経営が上向きになっても、予期しない別の原因で経営悪化になる可能性もあります。
そのような事態になっても、すぐに打開策が浮かび上がる発想力・臨機応変に対応できる瞬発力が、経営コンサルタントには必要です。
公務員のような決まった時間・決まった事務仕事を黙々とこなすのが得意という人は、経営コンサルタントには不向きといえるでしょう。
常にポジティブシンキングな人
経営コンサルタントはクライアントが抱えている問題・悩みに対処する仕事です。なかには、他社さえも業績回復できなかった難解な案件も来るかもしれません。
しかし、クライアントの要望にしっかりと応えて成果を見せるのが、経営コンサルタントの仕事です。諦めずに意気消沈しているクライアントの経営者や従業員を励まして、少しでも業績の回復をする心構えを持っていないと、経営コンサルタントは務まりません。
少しのネガティブな材料があるだけで、悪い方向にしか発想できないタイプは、経営コンサルタントは向いていないといえます。
コミュニケーションスキルに長けている人
経営コンサルタントは、クライアントと向き合ってそのクライアントが抱えている問題・悩みを浮き彫りにするのが、業務内容の第一歩です。しかしクライアントのなかには人と話すのが苦手な人、自分の考えを上手に伝えられない人もいます。
そのような人をリラックスさせて話しやすい雰囲気に持っていくこと、うまく考えを引き出すことも、経営コンサルタントの仕事の一つです。
経営に関する知識・スキルも重要ですが、それ以上に多くの人たちと出会って対面で、さまざまな話を聞くのが好きな人、それが苦痛でない人は、経営コンサルタントに向いているといえます。
シンクタンクに向いている人
シンクタンクに向いている人は、以下のような特徴があります。その特徴を紹介しましょう。
探究心が強い・貪欲な人
シンクタンクでの主な業務は、さまざまな事案に対して研究・分析・解析を行なうことです。現状に満足せず常に高度で精度の高い提案・研究成果を公表する人こそ、シンクタンクの業務が向いているといえます。
専門性の高い知識・スキルに長けている人
シンクタンクの業務は、精度の高い成果を出すために専門性の高い知識・スキルを持ち合わせていないといけません。他の業種であれば、特別なスキルや資格などを所有していなくても、やる気さえあれば良い仕事ができるものもあります。
しかしシンクタンクはそのような業種ではなく、一般では複雑で難解な案件にも対応しなくてはいけないため、ハイレベルな能力が必要です。
そのような専門性の高い業務に対応できる人、あるいはそのような業務をやってみたい人に、シンクタンクの業務は向いています。
ハイレベルな環境で仕事をしたい人
シンクタンクに所属する人材は、高度で専門性の高い知識・スキルを兼ね備えたエキスパートが揃っています。そして、対応する案件も、一般では取り扱わない国家・行政レベルの案件も決して珍しくありません。
そのような、同じ職場の人間・クライアントともに、ハイスペック・ハイレベルな人たちと接して、人間として大きく成長したい、あるいは高収入を狙いたいという人は、シンクタンクでの業務が向いています。
そのようなハイレベルな環境に所属するためには、自らも対応できるように努力をしなくてはいけません。ある程度の収入であれば満足といった具合に現状に満足する人でなく、常にレベルの高い環境に自分を置いて自分を磨きたいという人は、シンクタンクがおすすめです。
おわりに
経営に関する業種として近年台頭してきたのが、経営コンサルタント・シンクタンクです。どちらも高い専門性が必要な業種ですが、両者には違いがあります。
将来、経営に関する仕事がしたい高校生の方々は、経営コンサルタント・シンクタンクの特徴やメリットなどを把握して、どちらが自分に適しているのか考えることが大事です。
最後に、日本経済大学の経営学部について紹介します。経営に関する豊富な知識・スキルが身につき、その人の特性に対応できるさまざまな学科・コースが用意されているのが特徴です。
日本経済大学には、経営ロジックを学べる経営学部が用意されています。経営学部は3つの学科に分類されており、そのなかでも総合的な経営学を習得できるのが、経営学科です。
経営学科では、合理的な経営ロジックをマスターして、ビジネスチャンスを活かせる知識・スキルを習得します。4年間の在学での学習・経験を経て、卒業後にさまざまな分野で活躍できる人材を育成するのが、学科の目的です。
経営学科は、生徒の目標・特性に対応できるように、以下のような6つのコースが用意されています。
- 総合経営コース
- アトツギ・起業家コース
- デジタルビジネスコース
- eスポーツ・アニメ産業コース
- 飲食ビジネスコース
- SDGs・環境ビジネスコース
総合的な経営学、起業、デジタル、スポーツ、エンターテインメント産業、飲食など、生徒一人ひとりの特性・志望に対応できる豊富なコースが用意されているのが特徴です。
経営学科での4年間は、以下のステップで進められます。
・1年次
経営の成り立ち・法律など、経営の基礎・知識を広範囲にわたって学習
・2年次
どのような分野の経営が自分に適しているのかを分析し、専門性を高める1年。生徒一人ひとりの興味・問題意欲に対応して専門的な探究心を養う。
・3年次
自分が指定した分野をより深く研究する1年。実践的な学習を体験して、社会に出た際の心構え、即戦力を身につける段階。
・4年次
入学から3年間で身につけた知識・スキル・体験を総括する1年。高度で専門性の高い知識。スキルの精度を高めて、どんな分野においても即戦力になれるような人材を育成。
・卒業
卒業後の進路・就職先は、保険・金融業、販売・製造業、音楽・マスコミ、サービス業・公務員などです。日本経済大学出身者は、各分野においてプロフェッショナルな活躍を見せています。