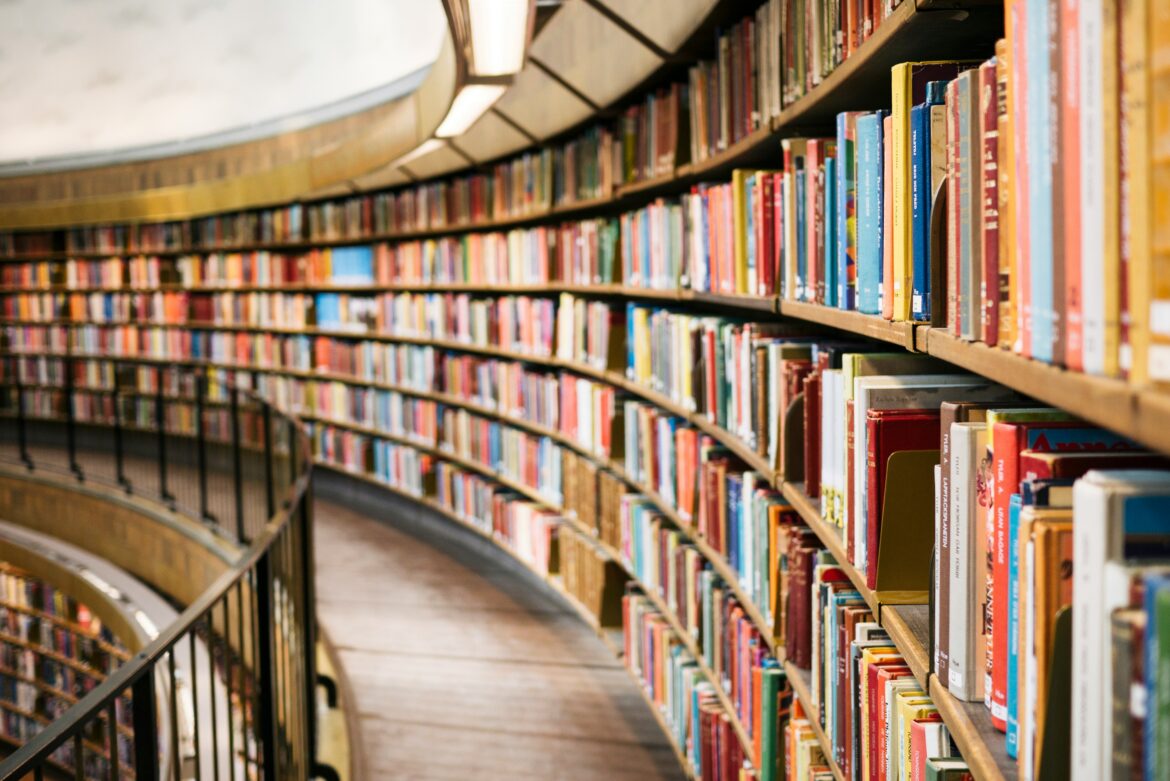帰国生入試の面接は、「海外経験そのものの珍しさ」を評価する場ではありません。評価されるのは、経験から何を学び、どのように思考と行動が変わり、大学でどう活かすか——この“学びの変換力”です。本記事では、テンプレートと質問例つきでわかりやすく示します。ただし、基本は共通する部分もありますが、詳細は各大学の最新要項をご確認するようにしてください。あくまでもサンプルとしてご確認いただけますと幸いです。
面接で見られる主な評価観点(共通項)
-
志望理由の一貫性:学部の学びと自分の関心・経験が論理的につながっているか。
-
思考の構造化:結論→理由→具体例→再結論といった論理展開(PREP/STARなど)。
-
再現性のある成長:一度きりの武勇伝ではなく、「次もできる」行動原理・習慣を示せるか。
-
協働性と多様性理解:異文化状況での相互理解・合意形成の姿勢。
-
言語運用力:日本語・英語いずれの場合も、相手に合わせて平易に正確に伝える力。
-
大学での具体的計画:入学後の授業・ゼミ・活動・将来像までの見通し。
国際経験を“学び”に変える万能フレーム「SEA→MAP」
-
S(Scene)状況:どんな場面・背景だったか
-
E(Event)出来事:何が起き、何が課題だったか
-
A(Action)行動:自分は何をしたか(役割・工夫)
→ M(Meaning)意味:そこから得た気づき・原理
→ A(Application)応用:別の場面でどう活かしたか
→ P(Plan)計画:大学での活用計画(科目・ゼミ・活動)
この「SEA→MAP」を使うと、単なる体験談が「検証可能な学びの物語」になります。
1分自己紹介の型(30秒/60秒対応)
-
結論:志望分野と一言強み(10秒)
-
根拠:海外での具体例(20秒)
-
接続:大学での学び計画(20秒)
-
締め:貢献の一言(10秒)
例(60秒):「○○学部を志望する理由は、異文化下での合意形成に関心があるからです。現地校のディベート部で多様な価値観が衝突する場面を経験し、立場要約→論点整理→代替案提示の流れを実践してきました。入学後はコミュニケーション論やデータ分析の科目で“合意形成の再現性”を検証し、学内外のプロジェクトで実装します。貢献できるのは、対話の場を前に進める推進力です。」
帰国生入試の“頻出質問10”と回答例
使い方:質問の“狙い”→回答テンプレ→例(短文)を示します。自分の体験に差し替えて練習してください。
-
なぜ本学部なのか。(狙い:適合性・一貫性)
-
テンプレ:結論(学びたい核)→経験との接点→入学後計画
-
例:「多文化環境での意思決定に関心があり、○○学部の○○科目が適合します。現地での生徒会で折衝役を担い、その過程を理論で検証したいです。」
-
-
海外経験で最も難しかったこと。(狙い:課題発見・対処)
-
テンプレ:状況→課題→具体行動→学び→再現計画
-
例:「価値観の対立で議論が停滞。全員の主張を要約し共通目標を再定義、合意に達しました。以後、会議前に合意プロトコルを準備しています。」
-
-
日本と海外の学校の違いをどう捉えるか。(狙い:比較のバランス)
-
テンプレ:事実の違い→良さと課題を双方提示→自分の活かし方
-
例:「評価方法や発言機会の設計が異なります。双方の良さを取り入れ、議論の見える化で貢献します。」
-
-
失敗から学んだこと。(狙い:メタ認知)
-
テンプレ:失敗→原因分析→改善→成果→今後の指針
-
例:「英語での早口が誤解を生み、要点を箇条書き提示に変えて合意が早まりました。」
-
-
多文化チームでの役割。(狙い:協働性)
-
テンプレ:役割→具体行動→成果→学び
-
例:「ファシリ役として、発言を日本語/英語で要約し議事録に反映、意思決定が短縮しました。」
-
-
関心のある社会課題を1つ。(狙い:知的好奇心・構造化)
-
テンプレ:課題定義→原因仮説→自分の関与→大学での探究計画
-
例:「観光と地域生活の調和。データと対話で合意形成のモデルを検証したいです。」
-
-
日本語(または英語)での学習に不安は。(狙い:自己把握と対策)
-
テンプレ:弱点の認識→具体対策→実施計画
-
例:「専門語の読解は継続強化中で、要約→用語カード化→週次テストを実施しています。」
-
-
高校で最も力を入れた活動(ガクチカ)。(狙い:主体性)
-
テンプレ:目的→行動→成果→汎化した学び
-
例:「文化祭の出店で在庫管理を設計し、欠品ゼロ。数理的な意思決定を学びました。」
-
-
将来像と大学での学びの接続。(狙い:計画性)
-
テンプレ:3年後・10年後像→必要スキル→大学計画
-
例:「合意形成の専門家を目指し、統計・組織行動・プロジェクト科目を段階的に履修します。」
-
-
最後に何か伝えたいことは。(狙い:要約力・当事者意識)
-
テンプレ:志望核→価値提供→短い決意
-
例:「多様性の中で前へ進める力で、学びとコミュニティに貢献します。」
逆質問の作り方と例
-
原則:募集要項でわかることは聞かない/学びへの当事者性を示す。
-
型:「興味領域 × 学内での具体の機会 × 自分の貢献」
例
・「○○領域のゼミで、学外プロジェクトに参加する機会はありますか。必要な前提知識があれば準備したいです。」
・「初年次に議論・発表機会を増やす取り組みはありますか。過去に司会進行で貢献した経験を活かしたいです。」
英語・二言語面接のポイント(帰国生向け)
-
平易さ>難語:専門用語は定義を添える(例:trade-off=「何かを得るために別の何かを犠牲にする」)。
-
切替の合図:「この点は英語で述べます」「日本語に戻します」と明示して混乱を防止。
-
通訳癖の回避:逐語訳ではなく要点要約で。
-
数値・固有名詞はゆっくり:聞き取りエラーを防ぐ。
-
想定問答12(英語版を準備):志望理由/強み弱み/conflict resolution/leadership/failure/future plan など。
集団面接・GD(グループディスカッション)の基本
-
最初の30秒:目的と時間配分を提案(例:「20分のうち10分で論点整理、8分で案出し、2分でまとめ」)。
-
役割:司会・書記・タイムキーパーのいずれかで貢献。
-
可視化:論点・仮説・反証を短語で板書。
-
合意形成:完全合意に固執せず、少数意見の条件付き採用案も提示。
-
評価の肝:人を“ねじ伏せる”のでなく“前進させる”ふるまい。
オンライン面接のチェックポイント
-
カメラ位置:目線と水平、顔の中央にスペースを残す。
-
音声:外部マイク推奨、環境音の遮断。
-
照明:顔の正面を明るく、逆光回避。
-
名前表記:フルネーム(ローマ字/漢字)を統一。
-
リスク対応文:「音声が乱れた場合、言い直しますのでお知らせください」。
-
予備:回線切替・デバイス充電・URL再入室手順を事前確認。
ポートフォリオ/提出物の“面接化”チェックリスト15
-
表紙に「関心領域・目的・期間」を明記
-
各活動を「SEA→MAP」で1ページ要約
-
定量(数・割合)と定性(声・変化)を併記
-
自分の“役割”を明確化(決めた/作った/変えた)
-
失敗と改善を1:1で記載
-
参考文献・参照情報の出所を簡潔に
-
用語は注釈で平易に
-
写真・図はキャプションで要点を一文化
-
日本語・英語の混在は節で分ける
-
大学での活用計画ページを最後に
-
ファイル名は「氏名_志望学部_ポートフォリオ」
-
5分説明用の“見せ順”を用意
-
1分版の口頭サマリーを練習
-
先生・家族以外の第三者にレビューを依頼
-
最新版の日付を明記
一週間で仕上げる面接対策プラン(汎用)
-
D-7〜5:志望理由と1分自己紹介を作成→録画→客観評価。
-
D-4:頻出10問に回答を作り、PREP/STARで整形。
-
D-3:逆質問を3本用意(科目・学び方・学内機会)。
-
D-2:オンライン環境の実地テスト。
-
D-1:要約カード最終確認・睡眠。
-
D-0:5分前接続、深呼吸、笑顔で入室/入室前礼。
伝わりにくい表現の言い換え
-
NG:「海外の方が○○、日本は△△」
→ OK:「私の経験した学校では○○、一方で日本の学校では△△という設計が見られました。双方の良さをこう活かしたいです。」 -
NG:「特にありません」
→ OK:「〜の点に課題を感じており、○○の方法で補います。」 -
NG:「努力します」
→ OK:「週3回の○○、月1回の△△を継続します。」
想定問答ミニ台本(日本語/英語混在の例)
-
Q:志望理由を英語で30秒で。
A:「I want to study how diverse teams make decisions. In high school debates, I learned to summarize claims and propose common goals. At university, I’ll test these methods in seminars and projects.」 -
Q:日本語で、失敗からの学びを。
A:「議論を急ぎすぎて合意が得られませんでした。以後、主張の要約→論点の整理→選択肢提示の順で進め、参加者の納得感が高まりました。」
面接当日の基本マナー(共通)
-
入退室:入室のノック・着席の合図・退出の礼を落ち着いて。
-
話速:結論を先に、1文短く。
-
非言語:うなずき、姿勢、手元は胸より下。
-
時間:質問終了の合図に合わせ、要約で締める。
-
感謝:最後に一言の御礼と学びの要約。
まとめ|“経験”から“学び”へ、そして“計画”へ
帰国生入試の面接対策は、経験の物語化(SEA)→意味づけ・応用(MAP)→大学での計画の三段構えで整います。頻出質問10に自分語を当てはめ、逆質問で当事者性を示し、当日は平易で構造的に伝える。この手法は、中立的な基本形でさまざまな場面でも活躍すると思われます。
【日本経済大学のキャンパスライフ】
日本経済大学は、単なる学問だけでなく、豊かなキャンパスライフを通じて学生たちの成長と個性の伸展を促進します。
キャンパス内では多彩なクラブやサークル、文化イベントが活発に展開され、学生たちは自分の興味や才能を発揮し、新たな交友関係を築くことができます。
学外活動も大いに奨励され、学生たちは都心の様々な文化やイベントに触れることができます。
これにより、卒業後には社会においても多様な価値観を理解し、柔軟な思考力を備えた人材として成長することが期待されます。
資格取得・奨励金給付制度を通じて、学生たちは自己成長に対する励ましを受け、自身の専門分野での深化を目指すサポートが充実しています。
この制度は、学業だけでなく、将来のキャリアにおいても大いに活かされることでしょう。
日本経済大学のキャンパスライフは、学問だけでなく、人間形成としての重要な役割を果たしています。
詳細は以下のホームページをご覧いただき、日本経済大学の魅力やキャンパスでの日々の活動に触れてみてください。
・日本経済大学HPホームページ
https://www.jue.ac.jp/
・日本経済大学 資格取得・奨励金給付制度
https://www.jue.ac.jp/qualification/
ぜひ、日本経済大学のキャンパスでの充実したライフスタイルをご体験ください。