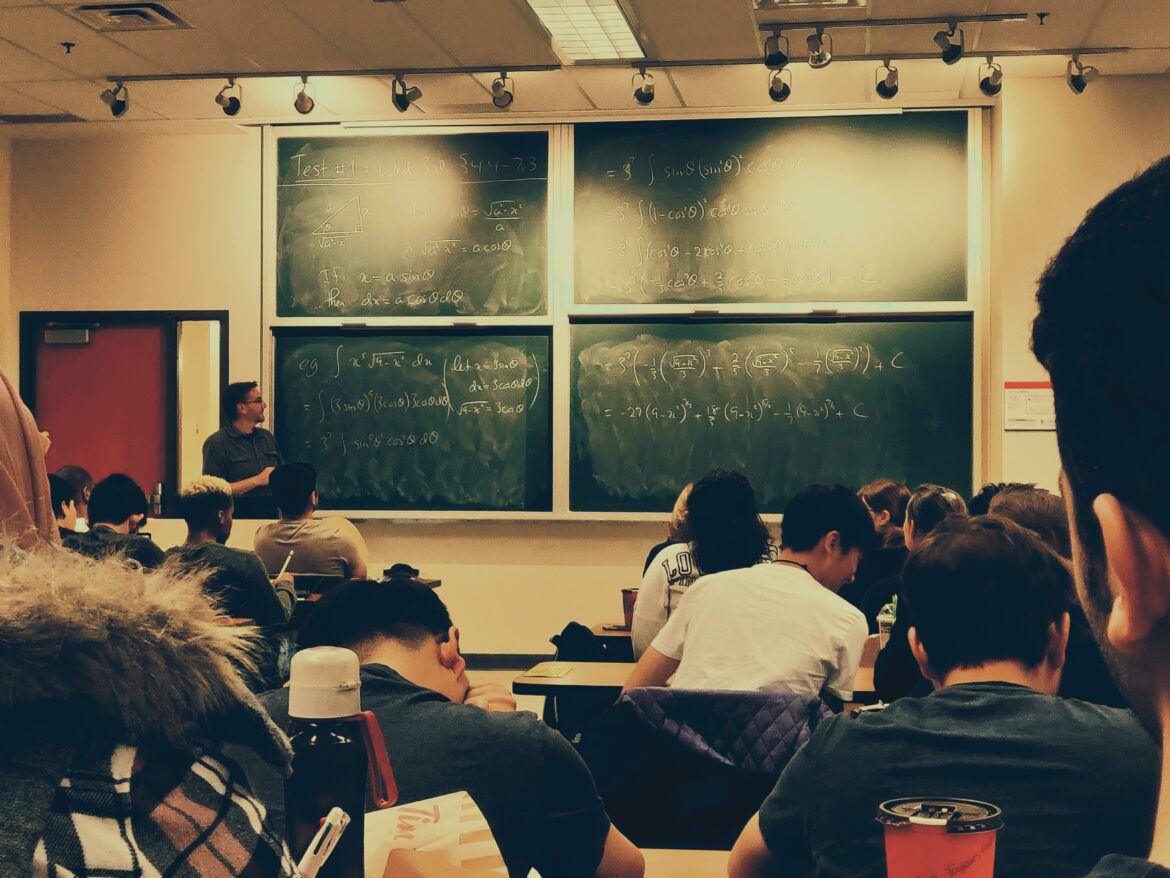教育の世界への第一歩を踏み出す際には、重要な選択が待ち受けています。小学校、中学校、高校とそれぞれの学校段階での教師の役割や仕事内容は異なります。また、それに伴って求められるスキルややりがいも変わってきます。
この記事では、教員としてのキャリアを考える際に知っておくべきポイントを解説します。まず最初に、教員としての基盤となる教員免許の重要性についてご説明します。さらに、小学校、中学校、高校の教師になるための方法やそれぞれの役割の違いについても紹介します。
1. 教員免許の重要性
①教員免許の種類
教員免許状は、教師になるために必要な資格であり、それぞれの学校段階や職種によって異なる3つの種類があります。
(1)普通免許状
・一般的に取得される免許で、教諭、養護教諭、栄養教諭の資格が含まれます。
・小学校、中学校、高校などの学校種や、教科ごとに分類されます。
普通免許状の詳細:
普通免許状にはさらに二種、一種、専修の区分があります。取得に必要な単位数が異なるため、教育機関によって取得できる区分が異なります。
専門学校・短期大学: 二種免許状
大学: 一種免許状
大学院: 専修免許状
二種、一種、専修の免許状の名前は異なりますが、実際に教員として働く際には違いはありません。クラス担任や授業を担当することができるのは、どの免許状を持つ教員も同様です。将来的に管理職を目指す場合、二種免許状から一種免許状に切り替えることができます。
(2)特別免許状
・社会人経験を積んだ人が、教員職に就くために取得する免許です。
(3)臨時免許状
・教育機関が普通免許状を持たない人に対して、教員職に就くために授与される免許です。
②教員免許の取得方法
教員免許状の取得方法は以下の3つがあります。
(1)教職課程のある大学・短大・専門学校で取得
一般的な方法で、講義や実習を通じて必要な単位を取得します。
(2)教員資格認定試験に合格する
教員資格認定試験を受け、合格することで免許状を取得します。
(3)教育職員検定に合格する
各教科の知識や経験を持つ人を学校現場に迎えるための試験です。
③教員免許の有効期限について
教員免許の更新制度は、2009年から導入され、10年ごとに30時間以上の講習を受けることが必要でした。この制度は、教員として必要な資質や能力を保持し続けるためのものでした。
●2022年7月1日からの変更
しかし、2022年7月1日から、教員免許状の更新制度がなくなりました。これにより、既に有効な教員免許状を持っている人は、無期限の免許状となり、更新のための講習を受ける必要がありません。
●免許状の新旧について
新免許状と旧免許状には以下のような違いがあります。
新免許状:
・現職教師: 失効
・非現職教師(ペーパーティーチャー): 失効
旧免許状:
・現職教師: 失効
・非現職教師(ペーパーティーチャー): 休眠
2.小学校、中学校、高校の教師になる手段
①小学校の教師になるには
小学校教師になるためには、大きく分けて3つの資格があります。
(1)小学校教諭専修免許状
大学院修士課程で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計91単位です。
(2)小学校教諭一種免許状
4年制大学で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計67単位です。
(3)小学校教諭二種免許状
短期大学で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計45単位です。
※ 二種免許状は現在、短期大学卒業程度で取得できる教員免許となっていますが、文部科学省では、2025年度より、4年制大学でも二種免許状を取得できる教職課程を新設できるよう、準備を進めています。将来的には4年制大学でも二種免許状の取得が可能になります。
②中学校の教師になるには
中学校教師は、専門教科の授業を行います。そのため、教科ごとに教員免許状が必要です。
例えば、国語を教える教師が持つのは「中学校教諭一種免許状 国語」、数学を教える教師なら「中学校教諭一種免許状 数学」などです。
資格には、大きく分けて3つの種類があります。
(1)中学校教諭専修免許状(教科)
大学院修士課程で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計91単位です。
(2)中学校教諭一種免許状(教科)
4年制大学で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計67単位です。
(3)中学校教諭二種免許状(教科)
短期大学の中学校教員養成課程などで学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計43単位です。
※ 二種免許状は現在、短期大学卒業程度で取得できる教員免許となっていますが、文部科学省では、2025年度より、4年制大学でも二種免許状を取得できる教職課程を新設できるよう、準備を進めています。将来的には4年制大学でも二種免許状の取得が可能になります。
③高校の教師になるには
高校教師も中学校教師と同様に、専門教科の授業を行います。
資格は、大きく分けて2つの種類があります。
(1)高等学校教諭専修免許状(教科)
大学院修士課程で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計91単位です。
(2)高等学校教諭一種免許状(教科)
4年制大学で特定の科目を学び、卒業することで取得できます。
取得に必要な科目の単位数は、教科および教科の指導法、教育の基礎的理解、教育実践、外国語コミュニケーション、情報機器の操作(または数理、データ活用および人工知能に関する科目)など、合計67単位です。
※ 高等学校教諭の普通免許状には、短期大学卒業で取れる「二種免許状」はありません。大学、大学院を卒業しないと高等学校教諭の免許を取得できないので、注意が必要です。
3. 小学校、中学校、高校の教師の役割と仕事内容の違い
小学校、中学校、高校の教師は、それぞれの学校段階において異なる役割を担います。
①小学校の「学級担任」の役割
小学校の教師は、学級担任制度を採用しています。これは、国語・算数・理科・社会を含む全教科と教科外活動(例: 外国語活動、学級会活動)を担当します。学級担任は、各児童の発達段階を総合的に把握し、個々の能力に合わせた教育を提供します。小学校では、義務教育の最初の6年間で基礎的な学力と社会性、協調性、人間性を育むことが重視されます。
②中学校の「教科」「生徒指導」「部活」の多様な仕事
中学校では、教科担任制度が採用されています。教科担任は、特定の教科(例: 英語、数学)を専門に教えます。これにより、授業の質や生徒の理解度を深めることができます。また、学級担任の業務には、進路指導、生徒指導、部活動の指導などが含まれます。中学校では3年間の義務教育が終了し、生徒の進路選択が重要になります。
③高校の「専門教科」「進路指導」
高校では教科担任制度が採用され、専門的な教科を担当します。文系科目や理系科目など、より専門的な学習が行われます。また、高校では進路指導が重要な役割となります。生徒の将来に向けた選択肢や判断基準を提供し、それぞれの進路に向けて具体的なサポートを行います。進学や就職など、生徒が自分自身の将来についてしっかりと考える一助になるでしょう。
進学や就職などの進路選択に向けて、生徒と保護者とのコミュニケーションが欠かせません。それぞれの教育段階での役割の違いを理解し、生徒たちの成長をサポートすることが、教師の重要な使命です。
4.小学校教師、中学校教師、高校教師のどれを選ぶか
小学校、中学校、高校での教師職を選ぶ際に考慮すべき要因は多く、個人の適性や希望によって異なります。
以下は選択のポイントです:
①適性に基づく教師職の選択ポイント
●小学校教師
・休日を確保しやすく、週末の出勤が少ない。
・長期休暇が部活動の影響を受けにくい。
・人間形成に影響を与える存在として、包容力と指導力が重視される。
●中学校教師
・専門の教科担任制で、教科知識が必要。
・12〜15歳の生徒とのコミュニケーションが重要であり、愛情と理解が求められる。
・生徒の成長を長い目で見守りながら、強い責任感と倫理観が必要。
●高校教師
・高い教養と専門知識が必要で、生徒に分かりやすく伝える能力が求められる。
・生徒との信頼関係の構築が重要で、個別のニーズに対応し成長をサポートする。
・忍耐力、柔軟性、情熱が必要であり、自己成長と学び続ける意欲が求められる。
②採用試験の難易度
小学校の教師の採用倍率は比較的低く、中学校や高校の倍率は高い傾向がある。採用試験の難易度を考慮するのもポイント。
各教師職は異なる要素が重要となりますので、自身の適性や志向に基づいて選択することが重要です。
おわりに
教育の現場で活躍する教師には、それぞれの学校段階で求められる独特の資質と役割があります。小学校教師は子どもたちの成長を見守り、基盤を築く存在。中学校教師は多感な時期の生徒たちに寄り添い、知識を授ける使命を担います。そして高校教師は、専門知識を通じて生徒たちの未来を切り拓く先駆者です。
自分の適性や志向に合わせて、どの学校段階で教師として活躍するかを選ぶことは重要です。そして、それぞれの選択にはそれぞれの魅力とやりがいがあります。
最終的には、どの学校段階でも、生徒たちの成長に貢献する教育者の使命感が最も大切です。教師を目指す皆さんにとって、充実したキャリアが築けることを心から願っています。
【日本経済大学の教職課程】 日本経済大学は、多様な学生を受け入れ、個性を伸ばし、文化の発展に貢献できる技術者を育成します。教員養成においても、個性の発見と発展を基本にし、グローバルな視野、柔軟な思考力、高度な専門性を持つ教員を育てます。 経済学部では、中学校教諭一種免許(社会)、高等学校教諭一種免許(地理歴史・公民)、商学科では高等学校教諭一種免許(商業)、健康スポーツ経営学科では中学校教諭一種免許(保健体育・高等学校教諭一種免許(保健体育)が取得可能です。 経営学部の経営学科では、高等学校教諭一種免許(商業)、中学校教諭一種免許(社会)が取得できます。 教職課程担当教員は、オフィスアワーを設け、学生の相談や教育実習指導、採用試験等合格の指導を行います。また、図書館・情報センターでは、教職課程に関する資料の閲覧や視聴が可能です。 興味がありましたら是非ホームページをご確認ください。 ・日本経済大学HPホームページ https://www.jue.ac.jp/ ・日本経済大学 教職課程 https://www.jue.ac.jp/department_top/teaching_course/