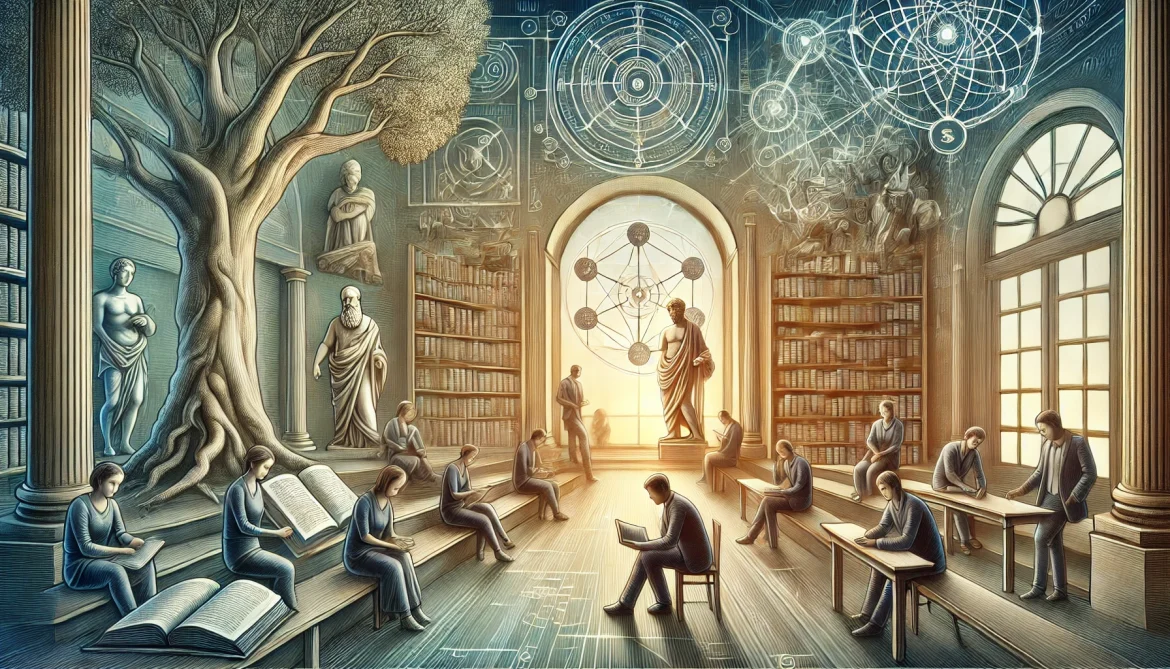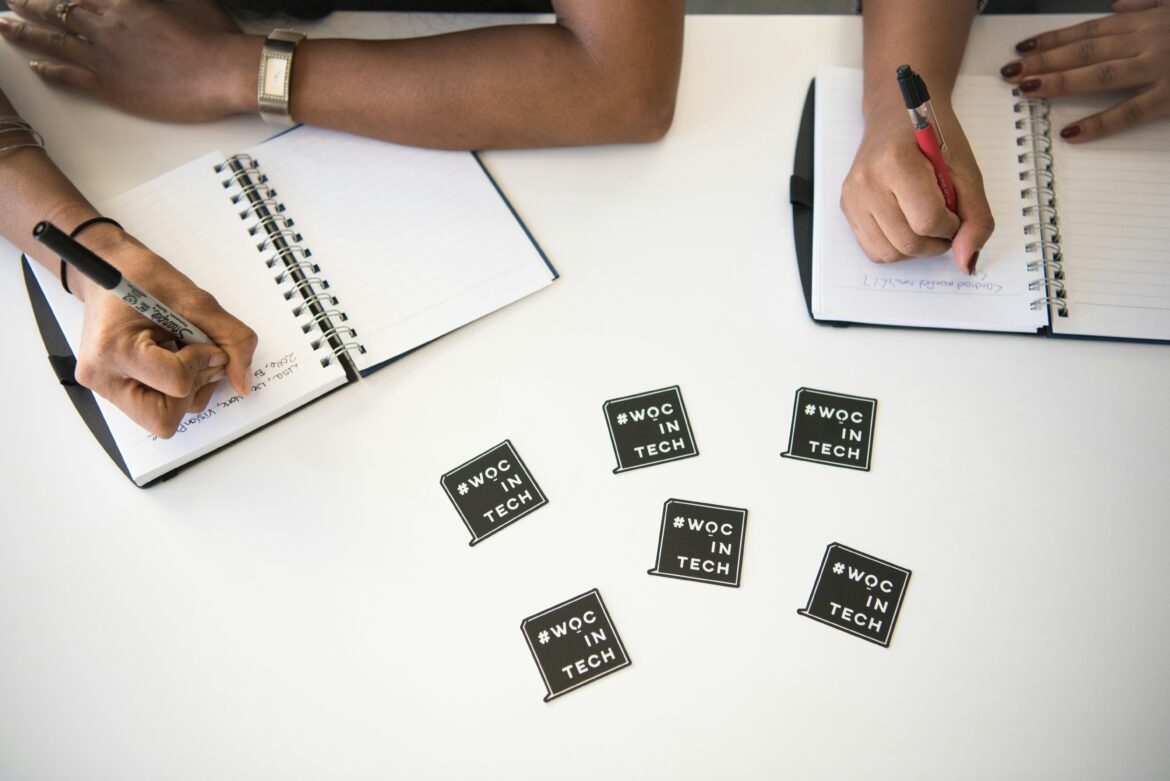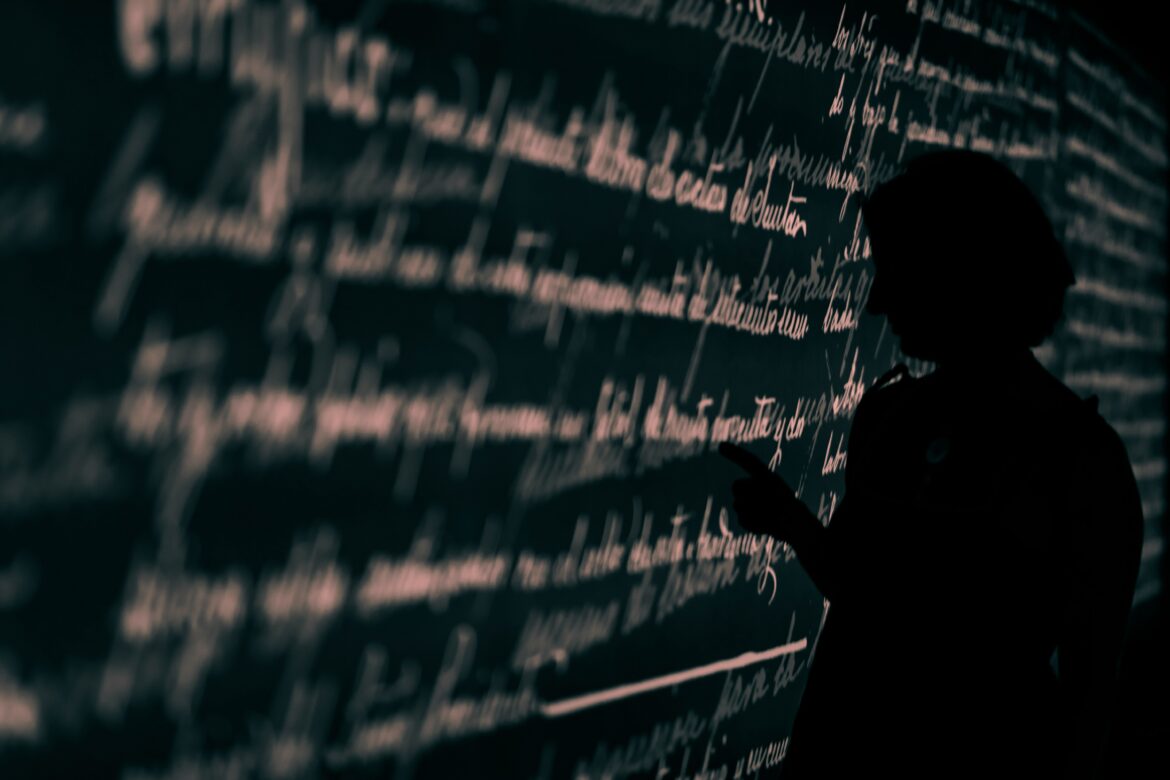日常生活の中で、「人生の意味とは何か?」や「本当の正義とは?」といった根本的な疑問を考えたことはありませんか?哲学は、こうした問いに真剣に向き合い、人間や世界の本質を探求する学問です。答えのない複雑な問いに挑戦し、物事を多角的に捉える力を身につけたいと感じるなら、哲学科での学びがあなたにとって理想的な道となるでしょう。
この記事では、哲学科を志望する理由を効果的に伝えるための書き方のコツと、実際に役立つ具体例をご紹介します。哲学への思いをどう伝えるか、そのヒントをぜひ見つけてください。
1. 哲学とは?
① 定義と概要
哲学は、世界や存在、人間の本質について根本的に問いかけ、考え続ける学問です。倫理、認識論、存在論など、多岐にわたるテーマを扱い、論理的な思考を通じて答えを追求します。哲学を学ぶことで、人生の意味や価値観、社会問題について深く考える力を養います。
② 現代における重要性
現代社会では、哲学的な視点がますます重要視されています。技術革新やグローバル化が進む中で、倫理や価値観、社会正義など、私たちが直面する課題は複雑化しています。哲学を学ぶことで、こうした問題に対する深い洞察力や、倫理的な判断を下す力を得ることができ、ビジネスや政治、教育などさまざまな分野でその知識を活かすことができます。
2. 哲学科の魅力とは?
①批判的思考と論理的分析力の養成
哲学科では、あらゆる問題や問いに対して批判的な視点を持ち、論理的に考える力を身につけることができます。哲学的な議論や論文執筆を通じて、事象や概念を深く掘り下げ、筋の通った考え方を構築するスキルが養われます。
②広い視野と多角的な思考
哲学科では、単に答えを求めるだけでなく、問いを立て、それを多角的に考察する力を学びます。これにより、複雑な問題に対する柔軟な思考や、新たな視点から物事を捉える力が身につきます。このスキルは、現代社会におけるあらゆる分野で役立つ能力です。
③グローバルな視点の獲得
哲学科では、古今東西のさまざまな哲学者の思想に触れることで、グローバルな視野を持つことができます。西洋哲学と東洋哲学を比較し、異なる文化や時代背景を学ぶことで、国際的な問題に対する理解を深め、異なる文化や価値観への理解を深めます。
④自己理解とアイデンティティの探求
哲学科での学びは、他者や社会だけでなく、自分自身を見つめ直す機会でもあります。哲学の根本的な問いを通じて、自己のアイデンティティや価値観について深く考え、自分の人生における選択や行動に対する意識を高めることができます。
3. 大学の哲学科で学ぶこと
大学の哲学科では、物事を深く考える方法や、論理的な思考力を身につけることができます。哲学のテーマはとても広く、「正義とは何か?」「人間の存在とは?」といった根本的な問いから、「時間や空間はどう感じられるのか?」という抽象的な考えまで、さまざまな問題に取り組みます。これらの問いに対して、自分で答えを見つけ出す力を養うのが哲学の大きな魅力です。
授業では、プラトンやデカルト、カントなど、有名な哲学者たちの考えを学ぶところからスタートします。彼らがどのように世界や人間について考えたのかを知ることで、哲学の基本的な考え方を理解できるようになります。哲学は西洋だけでなく、東洋の思想も扱い、さまざまな文化や時代背景の違いを学ぶことができる点が特徴です。
また、哲学の勉強には、文章をじっくり読んで理解する力が求められます。そのため、哲学書を原文で読むために、英語だけでなく、ドイツ語やフランス語といった外国語を学ぶことが推奨されることもあります。これは、外国語を通して、より深くその哲学者の思想を理解するためです。
さらに、哲学科では少人数のゼミ形式の授業が多く、先生や同級生と一緒に討論を行う機会がたくさんあります。このような討論を通じて、他の人の意見を尊重しながら、自分の考えを論理的に話す力が身につきます。また、さまざまな視点から物事を考える力も養われるため、実社会で役立つ思考力や問題解決能力を高めることができます。
1年生や2年生のうちは、哲学だけでなく、他の分野の授業も多く受けることができます。これにより、幅広い知識を身につけながら、3年生や4年生になると専門的な哲学の授業が増え、さらに深いテーマに取り組むようになります。最終的には、哲学科での学びを活かして卒業論文を書くことが多く、自分の興味を深く追求できるチャンスです。
4. 志望理由に含めるべきポイント
①個人的な興味
なぜ哲学に興味を持ったのか、どんな経験がきっかけで哲学に対する情熱が生まれたのかを具体的に説明しましょう。例えば、哲学書を読んだ経験や、学校の授業で議論を通じて新たな視点を得たことなど、哲学を深く学びたいと感じた瞬間を交えると説得力が増します。
②学科で学びたいこと:
哲学科で具体的にどのようなテーマや分野を学びたいのかを明確に示しましょう。たとえば、「倫理学を通じて現代の社会問題に対するアプローチを学びたい」や、「東洋と西洋の哲学を比較し、異なる文化における人間理解を深めたい」といった具体的な目標を伝えると良いです。
③ 将来の目標との関連性
哲学科で学ぶことが、将来の目標やキャリアにどう結びつくのかを説明しましょう。たとえば、「教育の分野で、哲学を通じて論理的思考力を教えたい」や「企業で倫理的な意思決定に貢献したい」といった具体的な将来像を描くことで、志望理由に現実味が加わります。
4. 志望動機の書き方のコツ
①具体的なエピソードを活用
志望動機には、自分自身の経験やエピソードを交えると、説得力が増します。例えば、「高校で哲学の授業を受けた際に、倫理的な問題に対する考え方が大きく変わり、その経験が哲学を深く学びたいという思いに繋がりました」といった個人的なエピソードがあると、志望理由がよりリアルに伝わります。
②大学の特徴に合わせる
志望する大学の哲学科が提供する特有のカリキュラムやプログラムについて言及し、それに魅力を感じた理由を述べましょう。たとえば、「〇〇大学の哲学科では、東洋哲学と西洋哲学をバランスよく学べる点に魅力を感じました」や、「△△大学の倫理学に関する講義を通じて、社会正義や人権に関する理解を深めたい」といった具体的な理由を挙げると効果的です。
③自己アピールを忘れずに
哲学科に適している自分の強みや特徴をアピールしましょう。たとえば、「物事を深く考える習慣があり、問題を多角的に分析する力に自信があります」や「他者の意見を尊重しながらも、自分の考えを論理的に主張できる力があります」といった具体的な強みを示すことで、哲学科での学びにどのように貢献できるかをアピールしましょう。
5. 志望理由書の具体例
具体例1:
ジブリ映画「君たちはどう生きるか」を観たことが、私が哲学に興味を持つきっかけでした。映画のタイトルの元ネタになった吉野源三郎の小説「君たちはどう生きるか」が母の本棚にあったので、映画との関係を知りたくて手に取ってみました。この小説は、15歳の少年が主人公で、おじさんとの交換ノートを通じて、自分の生き方や人との向き合い方を考える内容です。哲学的なテーマが含まれていながら、読みやすく、私は夢中でページをめくりました。
その中で、主人公が自分の行動を見直し、どう生きるべきかを深く考える姿に強く共感しました。私自身も、普段の生活で正しい行動とは何か、他者にどう接するべきかといった問いに向き合うことがあり、この本を通じて、それが哲学的な問いであることを知りました。哲学が、人生の根本的な問題に向き合うための重要なツールであることを実感し、もっと深く学びたいという気持ちが芽生えました。
〇〇大学の哲学科では、倫理学や存在論など、私が興味を持ったテーマを体系的に学ぶことができ、さらに多様な哲学的視点を身につけられる点に強く惹かれています。また、少人数制のゼミナールで他の学生や先生と議論を深めることで、より論理的で柔軟な思考力を養い、自分自身の生き方や価値観についても考察を深めていきたいです。
将来は、哲学的な思考を活かし、教育や社会貢献の分野で活躍し、他者に深く考える力を伝えていきたいと考えています。〇〇大学の哲学科で学び、自分の人生と社会にどう向き合うべきかをさらに探求していきたいです。
具体例2:
私は高校時代に倫理の授業を受けた際、哲学が持つ深い思考力と多角的な視点に興味を持ちました。特に、存在論や倫理学において、人間の存在や価値観について考えることが、私にとって非常に刺激的でした。また、歴史的な哲学者の思想に触れることで、彼らが直面した社会問題や倫理的課題に対するアプローチを学び、自分自身の考えを発展させることができました。この経験を通じて、哲学の世界に強い興味を抱くようになり、さらに深く学びたいと感じました。
△△大学の哲学科では、古代から現代に至るまでの哲学者の思想を幅広く学び、それを現代の社会問題に適用する力を養える点に魅力を感じています。また、貴学で提供されているフィールドワークプログラムを通じて、社会の現場で哲学をどのように実践できるかを探求したいと考えています。さらに、貴学での議論を通じて、多様な視点を取り入れながら、自分自身の哲学的な考えを深めたいです。
将来は、公共政策の分野で、倫理的な意思決定をサポートする役割を担いたいと考えています。また、哲学を通じて、多くの人々に論理的思考の重要性や倫理的な判断の価値を伝える活動をしたいと考えています。△△大学での学びが、私の将来の目標を達成するための確固たる基盤になると確信しています。
おわりに
哲学科への志望理由を伝える際には、自分の経験や興味を具体的に示し、学びたいことと将来の目標をしっかりと盛り込むことが重要です。この記事で紹介したポイントや具体例を参考に、あなたらしい志望動機を書き上げてください。
【日本経済大学の紹介】 日本経済大学は、経済学と経営学に特化した専門性の高い教育を提供する単科大学です。福岡、東京渋谷、神戸三宮にキャンパスを構え、特に東京渋谷キャンパスでは、多国籍な留学生が学ぶ環境が整っており、グローバルな視野を持つ経済人の育成に力を入れています。 ●日本経済大学の特色と強み 経済・経営系専門大学としての独自性と専門性: 日本経済大学は、経済学と経営学の深い理解と実践的なスキルを学生に提供し、高度な専門知識を持った経済人を育成しています。 ・異文化交流の活発なキャンパスライフ: 世界各国からの留学生が在籍しており、学内での国際交流は日常的なもの。異文化理解と国際感覚を養う絶好の環境があります。 ・名門海外提携大学との連携: 多彩な留学プログラムを通じて、国際的な経済人を目指す学生を支援。海外での学びを通じて、グローバルな視野を拡げる機会を提供しています。 ・デジタル教育の推進: 「デジタルを活用した大学・高専教育高度化プラン」の実施機関として選ばれ、最先端の教育環境を整備。情報社会に対応したスキルの習得を促進しています。 ・充実した就職支援: 幅広い業界との連携により、学生のキャリアサポートを積極的に行い、高い就職率を実現しています。 ●日本経済大学で学ぶメリット ・実践的な経済学・経営学の学び: 現実のビジネスケースやデータを用いた講義が豊富で、理論だけでなく実践的な知識とスキルの習得が可能です。 ・国際的な学習環境: 多国籍な学生との交流を通じて、国際的なビジネスシーンで活躍するためのコミュニケーション能力や異文化理解を深めることができます。 ・将来のキャリアパスの多様性: 経済学や経営学の専門知識を活かして、金融、商社、情報通信、国際機関など、多彩な分野でのキャリアを目指せます。