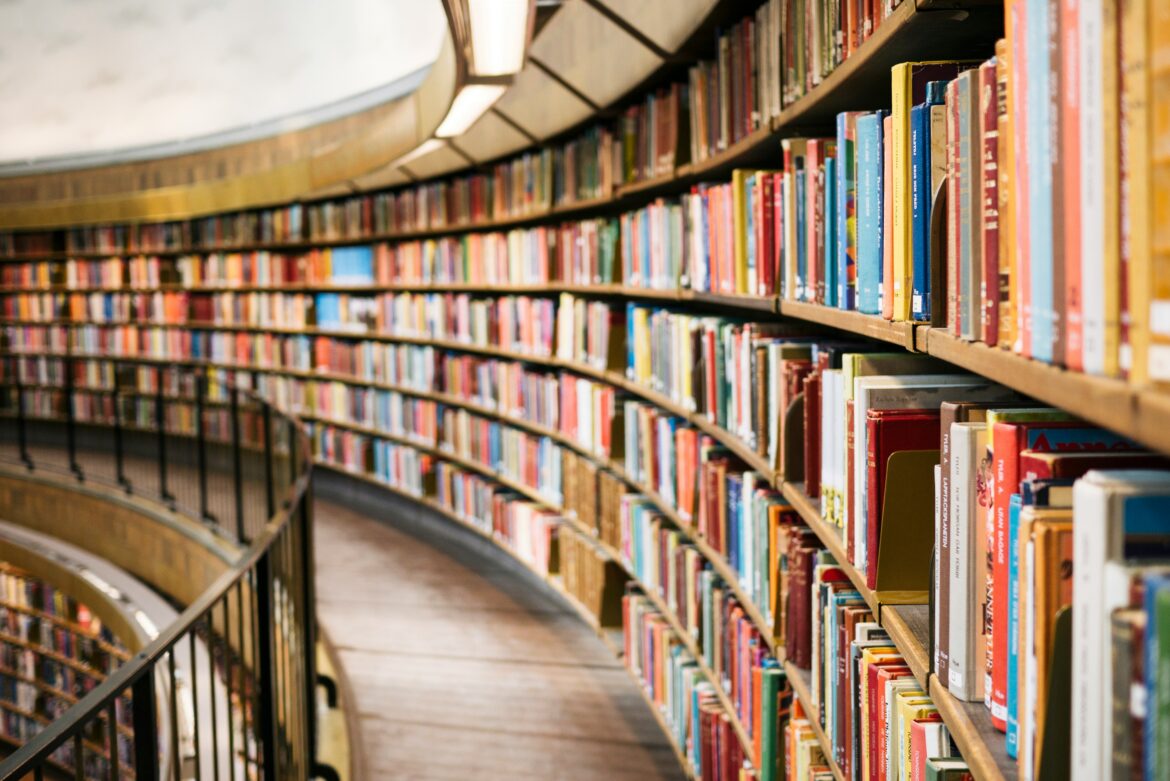はじめに:社会全体で求められる「ウェルビーイング」の価値
現代社会では、経済的な豊かさや物質的な成功だけでなく、人間の幸福(ウェルビーイング)そのものが、重要な評価基準として位置づけられるようになっています。持続可能な社会の構築、多様性の尊重、健康と福祉の確保、働き方の見直し――こうした一つひとつの課題が、「よりよく生きること(Well-Being)」という概念と密接に関係しています。
こうした流れの中で、近年、多くの大学で「ウェルビーイング学部」やそれに類する学科・プログラムが新設される動きが見られるようになりました。
本記事では、「ウェルビーイング学部の志望理由」を深掘りしていきます。第一パートでは、まずウェルビーイングという言葉の意味や、その学問的・社会的背景について解説します。
「ウェルビーイング」とは?──定義と広がる概念
「ウェルビーイング(Well-Being)」とは、直訳すれば「良好な状態」「幸福」「満足した生き方」などを意味します。国連やOECDなどの国際機関もこの概念を重視しており、たとえば**OECDの「より良い暮らし指標(Better Life Index)」**では、所得や雇用だけでなく、健康、教育、生活満足度、社会的つながりなど、多面的な指標によって「豊かさ」が測定されています。
日本でも、内閣府が2021年に「国民のウェルビーイングの向上」を基本方針として打ち出すなど、個人と社会全体の「より良い在り方」を考えることが政策レベルでも注目されています。
このように、「ウェルビーイング」とは単に「幸せな気分」という感覚的なものではなく、科学的・社会的な裏付けを持つ概念へと進化しているのです。
なぜ「学問」としてウェルビーイングを学ぶ必要があるのか?
これまで「幸福」や「生きがい」といったテーマは、哲学や心理学の一部領域として扱われてきました。しかし、現在のウェルビーイング学は、それにとどまりません。
心理学、教育学、社会学、公共政策、ヘルスケア、ビジネス、デザイン、ICT(情報通信技術)など、複数の学問分野が融合しながら、人々の暮らしや社会制度をより良くする実践的なアプローチを探求するのが、ウェルビーイング学の特徴です。
つまり、ウェルビーイング学部では以下のような観点から学びが進められます:
-
人の心と身体の健康を支える知識と技術
-
多様な価値観を認める共生社会のあり方
-
持続可能な働き方やコミュニティづくり
-
エビデンスに基づく幸福度の測定と政策提言
こうした学びは、現代のさまざまな社会課題に対する「実践的な答え」を提供する力となり、福祉・教育・行政・企業など幅広い領域でのキャリア展開にもつながるとされています。
高校生・受験生から注目される背景
近年、「自分がどのような人生を送りたいか」「社会にどう貢献したいか」を重視する高校生が増えています。ウェルビーイング学部は、まさにそうした**“自分自身と向き合う視点”と“社会的な課題意識”**の両方を育てる学問領域です。
-
人の幸福や生きがいに関心がある
-
社会問題の解決に関わる仕事がしたい
-
教育・福祉・医療・まちづくりに興味がある
-
自分の価値観を軸に学びたい
こうした志向を持つ受験生にとって、ウェルビーイング学部は理想的な学びの場であり、志望理由としても非常に説得力のあるテーマとなっています。
1. 各大学でウェルビーイングをどう学ぶか?
【1】心理・福祉・健康を中心とするアプローチ
― 武蔵野大学「ウェルビーイング学部」を例に ―
2024年4月、武蔵野大学は世界で初めて「ウェルビーイング学部」を開設しました。この学部は、個人・社会・地球全体の“より良い在り方”を追求する新しい学びの場として注目を集めています。
◉ 学びの特徴
武蔵野大学ウェルビーイング学部のカリキュラムは、理論と実践をバランスよく組み合わせながら、「真の幸福」を科学的にデザインする力を育成します。
以下のような構成で、段階的かつ体系的に学びが進んでいきます:
■ 段階的・体験的な学修のステップ
-
建学の精神の理解
幸せを追求する学問の土台として、仏教に基づく武蔵野大学の建学理念について学びます。 -
ウェルビーイング・デザイン/リテラシーの習得
自己・他者・社会・自然環境との関係性を捉え、幸福を「構想し」「行動に移す」力を身につけます。 -
5つの体験的テーマで探究
-
自己理解
-
自然・環境
-
地域・医療・福祉
-
ビジネス
-
国際理解
などを通じて、複数の領域からウェルビーイングの本質を捉えます。
-
-
未来デザイン・卒業プロジェクト
「ウェルビーイングな人生」「製品・サービス」「教育」「コミュニティ」など、自らの関心に基づいて具体的な提案・制作・実践を行います。
◉ 育成される人物像と将来像の例
考えられる例として、社会的役割を担う人材の育成を目指しています.
特に注目されるのは、単に知識を身につけるだけでなく、「自らの幸せと、社会の幸せを同時にデザインする力」を重視している点です。
これまでのパートではウェルビーイングの概念と社会的背景を、第二パートではウェルビーイング学部の設置校や学びの特徴を解説してきました。
こうした背景と学びの特徴を踏まえ、「志望理由の書き方」や「面接での伝え方」に焦点を当てて解説します。ウェルビーイング学部を志望する上で大切な視点や、伝え方の工夫を整理しながら、実際に使えるテンプレートや例文も紹介します。
1. 志望理由を書く前に整理すべき3つの視点
ウェルビーイング学部を志望する際は、以下の3点を軸に、自分の考えや関心を整理しましょう。これは、第一・第二パートの内容と結びつけながら言語化することが大切です。
① なぜ「ウェルビーイング」に関心を持ったのか?
第一パートで紹介したように、現代社会は孤立や不安、多様化する価値観に直面しています。そうした中で、**「人の幸せ」や「心と身体の健康」、「社会的なつながり」**を支えることの重要性に共感した経験を思い出しましょう。
例:
-
子どもや高齢者の孤立と貧困に関心がある
-
精神的な生きづらさを抱える人の支援がしたい
-
自分自身の経験を通じて、社会に還元したいと思うようになった
② なぜ「この大学・この学部」なのか?
第二パートで紹介したように、ウェルビーイング学部では「学際性」「実践性」「地域との連携」などが特徴です。大学ごとのカリキュラムに触れながら、自分の志向や関心と一致している点を述べましょう。
例:
-
福祉・心理・教育を横断的に学べる点に惹かれた
-
地域住民との協働フィールドワークができる環境に魅力を感じた
-
データ分析や行動科学など新しい視点も取り入れている点が先進的だと感じた
③ 将来、どう活かしたいのか?
ウェルビーイングの学びを通じて、どのような職業や社会的貢献を目指すのかを明確にしましょう。「社会課題の解決」や「個別の支援」など、目的意識を具体化することで説得力が増します。
例:
-
子どもの心のケアができるスクールカウンセラーになりたい
-
地域の福祉施設で孤立予防に取り組みたい
-
高齢者と若者がつながる地域づくりを推進したい
2. 志望理由の構成例
■ 構成テンプレート(基本形)
-
ウェルビーイングへの関心(背景・体験など)
-
志望大学・学部の魅力(カリキュラム・教育方針)
-
将来の目標・社会貢献のビジョン
■ 志望理由例文(修正版)
私は、人の「心の健康」と「社会的なつながり」を支える仕事に関心があります。現代社会では、孤立や不安が社会課題となっており、誰もが安心して暮らせる社会の実現に貢献したいと考えるようになりました。
貴学のウェルビーイング学部では、福祉・心理・教育を横断的に学べるカリキュラムに加え、地域と連携したフィールドワークが充実していると知り、実践を通じた学びに大きな魅力を感じました。
将来は、地域に根ざした福祉や教育の現場で、生きづらさを抱える人々に寄り添える専門職として社会に貢献したいと考えています。
3. 面接での伝え方のポイント
面接では、書いた志望理由を自分の言葉で自然に話すことが求められます。そのためには、内容を理解したうえで、話す練習を重ねることが大切です。
▶ 面接準備のポイント
-
書いた志望理由を声に出して読む練習をする
-
「なぜこの大学?」「なぜウェルビーイング?」に一言で答えられるようにしておく
-
自分の体験や背景をエピソードとして話せるように準備する
▶ 面接での好印象のポイント
-
笑顔、アイコンタクト、落ち着いた口調を意識
-
最初に「私は○○に関心があり〜」と簡潔に伝える
-
「3つの理由があります」など、話の構造を見せると聞き手が理解しやすい
最終まとめ
ウェルビーイング学部を目指すうえで、社会背景と大学の特色を自分自身の関心や将来像と結びつけて言語化することが、志望理由・面接ともに大きな鍵になります。
-
「なぜウェルビーイング?」は社会課題との関心軸で
-
「なぜこの大学?」は学びの特徴と自分の志向性を照らし合わせて
-
「将来どうなりたいか?」は具体的な職業や貢献の形で描く
志望理由の説得力は、情報理解×自己分析×伝え方の工夫の三位一体によって生まれます。
あなたらしい言葉で想いを伝えてください。
【日本経済大学のキャンパスライフ】
日本経済大学は、単なる学問だけでなく、豊かなキャンパスライフを通じて学生たちの成長と個性の伸展を促進します。
キャンパス内では多彩なクラブやサークル、文化イベントが活発に展開され、学生たちは自分の興味や才能を発揮し、新たな交友関係を築くことができます。
学外活動も大いに奨励され、学生たちは都心の様々な文化やイベントに触れることができます。
これにより、卒業後には社会においても多様な価値観を理解し、柔軟な思考力を備えた人材として成長することが期待されます。
資格取得・奨励金給付制度を通じて、学生たちは自己成長に対する励ましを受け、自身の専門分野での深化を目指すサポートが充実しています。
この制度は、学業だけでなく、将来のキャリアにおいても大いに活かされることでしょう。
日本経済大学のキャンパスライフは、学問だけでなく、人間形成としての重要な役割を果たしています。
詳細は以下のホームページをご覧いただき、日本経済大学の魅力やキャンパスでの日々の活動に触れてみてください。
・日本経済大学HPホームページ
https://www.jue.ac.jp/
・日本経済大学 資格取得・奨励金給付制度
https://www.jue.ac.jp/qualification/
ぜひ、日本経済大学のキャンパスでの充実したライフスタイルをご体験ください。