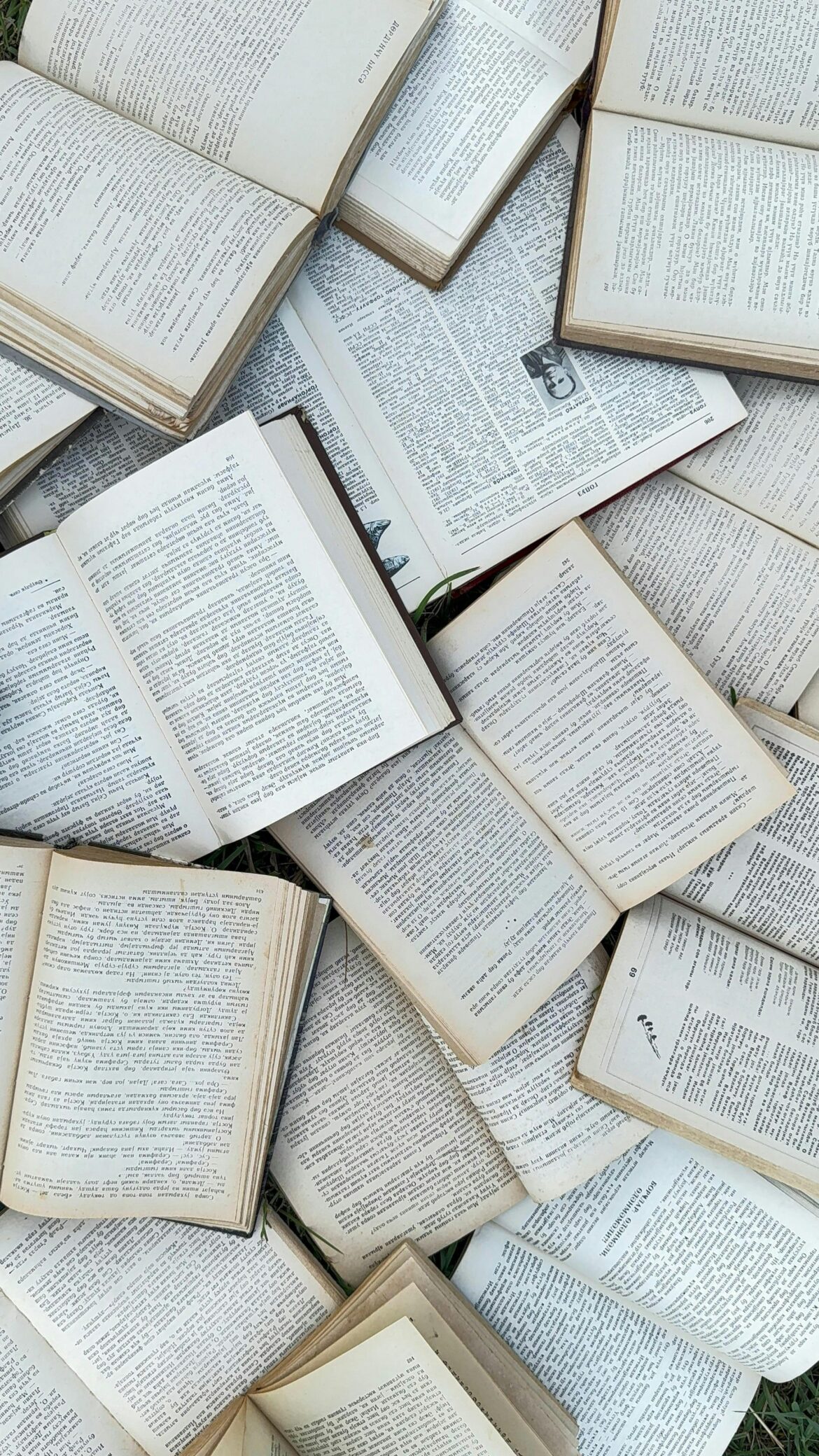本記事は、大学が目指す教育理念と入試方針に沿って、受験生が自らの経験を整理し、AO入試の面接で等身大の言葉で伝えられるように支援する「学習ガイド」です。特定の回答や攻略法を提示するものではなく、合否を左右するポイントの“考え方”を中心に解説します。
1. AO入試の全体像を理解する
1-1. 歴史と背景
AO入試(アドミッション・オフィス入試)は、1990年代後半から日本の大学で本格的に導入が進み、現在では多くの大学で幅広い分野に広がっています。学力試験の得点だけでは測りきれない意欲・個性・将来性を評価するという発想は、アメリカで発展したアドミッションの考え方を参照しつつ、日本の高等教育が重視してきた「多様な学び」と融合してきました。初期は国際系や芸術系などで先行導入されましたが、今日では理工系、経済・経営系、教育系、情報系などにも普及し、入学者選抜の重要な柱になっています。
1-2. AO入試の目的
AO入試の根本にあるのは、入学後に自律的に学び、社会へ新しい価値をもたらす学生を見いだすことです。大きく次の3点に整理できます。
-
多様な学生の受け入れ:学力試験の点数だけでは評価しにくい、探究心・コミュニケーション・協働性・課外活動の経験などを含む幅広い資質を見ます。
-
大学との相性の確認:受験生の関心や目標が、その大学・学部の教育内容、学修環境、研究文化と整合しているかを確かめます。
-
主体的学びの促進:入学後に自分で課題を設定し、試行錯誤しながら学びを深められるか。面接はその素地を対話的に見極める機会です。
1-3. 一般入試とのちがい(観点別の比較)
AO入試と一般入試は、評価の軸と準備のプロセスが異なります。以下の観点で対比すると捉えやすくなります。
-
評価基準:AOは面接、提出書類(活動報告書・志望理由書・学修計画など)、小論文やプレゼンテーション等の総合評価。一般入試は主として筆記試験の得点で評価。
-
合否の判断材料:AOは人物面(動機・経験の具体性・将来像)に加えて基礎学力の確認。一般は試験の点数が中心。
-
準備の流れ:AOは数か月〜1年以上をかけ、経験の棚卸し・自己理解・記述と対話の練習を重ねるのが一般的。一般入試は試験範囲の学習を計画的に積み上げ、直前期に演習量を高める。
-
利点と留意点:AOは個性や適性が評価されやすい一方で、表現の質や具体性が不足すると伝わりにくい。一般入試は評価が明快だが、当日の体調や一回の点数に影響されやすい。
大学公式メディアとしてのメッセージ
どちらが「有利」かではなく、自分の学び方と将来像に合う道を選ぶことが大切です。
2. 自己PR・志望理由の「伝わりやすい整理法」
本学が面接を通じて確認したいのは、きれいな模範解答ではなく、経験に裏づけられた言葉と学びへの具体的な関心です。ここでは「評価しにくい表現になりやすいパターン」と「より伝わる整理の仕方」を示します。あくまで考え方の参考としてお読みください。
2-1. 自己PRの例
-
抽象的になりやすい表現
例:「私は明るく元気な性格です。」
→ 事実かどうかを判断しにくく、大学でどう活かすかが見えません。 -
伝わりやすい整理
例:「高校の文化祭で実行委員長として、対立した意見を議論の場で可視化しました。各班の目標を一枚のシートに整理し、意思決定の基準を共有した結果、前年より来場者数が増え、スケジュール遅延も解消できました。私はこの『場を整える力』を、ゼミ運営や学生プロジェクトで活かしたいと考えています。」
→ 事実(出来事)→ 行動 → 結果 → 学び → 活用イメージの順で述べると具体性が高まります。
2-2. 志望理由の例
-
汎用的になりやすい表現
例:「家から通いやすく、学費が比較的安いからです。」
→ 他大学でも成り立ってしまうため、相性の確認には不十分です。 -
伝わりやすい整理
例:「地域経済に焦点を当てた授業や、学外での実践を伴うプログラムに関心があります。高校で商店街の活性化活動に参加した経験から、データに基づく現状分析と現場の対話の両立が重要だと感じました。カリキュラムの中で地域調査や企業インターンに取り組み、将来は地元企業の経営支援に携わりたいと考えています。」
→ 経験と大学の具体的な学びを結びつけることで、なぜその学部で学びたいのかが伝わります。
ワンポイント:固有名詞(授業名、研究テーマ、プロジェクト名)や数字、役割などを適切に織り込むと、主張の輪郭がはっきりします。ただし、公開情報を正確に確認し、誇張は避けましょう。
3. 面接で扱われやすいテーマ(検討の出発点になる質問例)
面接は受験生の内面を理解するための対話です。以下の質問例は、事前に自分の言葉で考えを整えるためのメモとして活用してください。回答の“正解”を暗記することが目的ではありません。
-
簡単な自己紹介
-
あなたの強みと、その根拠となる経験
-
最近の高校生活で最も力を入れたこと
-
困難に直面した場面と、乗り越えるためにとった行動
-
本学を志望した理由
-
学部・学科に関心を持った背景
-
履修してみたい授業やカリキュラムと、その理由
-
大学で挑戦したいこと(学修・課外の両面)
-
卒業後に考えている進路や将来像
-
関心のある社会課題と、あなたの見解
-
その課題に向き合うときの自分の役割
-
部活動・生徒会・ボランティア等で得た学び
-
リーダーシップやフォロワーシップを発揮した経験
-
チームで活動するときに心がけていること
-
尊敬する人物(身近な人を含む)と、その理由
-
失敗体験から得た学びと次への活かし方
-
大学生活の時間管理についての考え
-
入学後、学内外でどのように貢献したいか
-
関心のある研究テーマやトピック
-
面接官に確認したいこと(学びの環境やサポート等)
4. 短時間でまとめるためのワークシート
頭の中で考えるだけでは、論点が増えるほど伝える順序が散らばりがちです。1分〜2分で語れる骨子を、以下のシートで整理してみましょう。各マスは1文以内を目安に、推敲は何度でも。
4-1. 自己PRシート(骨子)
-
強み(結論):例)粘り強く課題に向き合える。
-
根拠:例)約束した役割を最後までやり遂げる習慣。
-
具体的エピソード:例)文化祭で予算不足に直面し、地域企業に協賛依頼。調整の結果、前年より来場者が増加。
-
大学での活かし方:例)ゼミ研究や学生プロジェクトで、論点整理と関係者調整を担う。
4-2. 志望理由シート(骨子)
-
きっかけ:例)高校の地域活性化プロジェクトを通じて経済学に関心。
-
大学の特徴(具体):例)地域経済に関する授業、実践型プログラム、少人数ゼミ。
-
自分との適合性:例)現場活動とデータ分析を往復する学び方に共感。
-
将来像:例)地元企業の経営支援を通じて地域の雇用創出に貢献。
4-3. 練習のコツ
-
要点はキーワードで記憶し、文章は毎回少しずつ変えて話す。自然さと一貫性が両立します。
-
録音や模擬面接で話し方を客観視。語尾の癖やスピード、間の取り方を確認。
-
数字・固有名詞は事実確認を徹底。信頼性は説得力の土台です。
5. 面接当日の心構えと想定外への備え
5-1. 答えに詰まったとき
-
深呼吸して3秒:短い沈黙は思考の時間。焦って早口になるより、落ち着きが伝わります。
-
前置きで考える余白をつくる:「考えを整理してお答えします。」など。
-
部分的に答える:結論が定まらないときは、現時点の見解や、検討中の論点を率直に述べる。
5-2. 想定外の質問が来たとき
-
意図を確認:「〜という観点で伺っていますか?」と確かめる。
-
自分の経験に引き寄せる:直接の回答が難しい場合でも、関連する経験や学びを手がかりに整理。
-
簡潔にまとめる:長考よりも、短く区切って対話のキャッチボールを続ける。
5-3. 緊張が高まったとき
-
姿勢と呼吸:椅子に深く座り、背筋を伸ばすと声が安定。
-
視線の置き方:相手の目が難しければ鼻・ネクタイ付近を見る。
-
表情:口角と頬を少し上げるだけで印象が和らぎます。
5-4. よくある“つまずき”と対応
-
話の途中で遮られた:要点を一言でまとめ、「続きは後ほど補足します」と柔らかく。
-
深掘りされた:背景・役割・工夫・結果の順で再整理し、必要なら数字を添える。
-
質問の意味が取りにくい:言い換えを求め、誤解を避ける。
-
意図と違う受け取られ方をした:「補足させてください」と前置きして軌道修正。
6. 公式メディアとしての留意点(読者へのメッセージ)
-
本記事は学びの姿勢づくりを支援する目的であり、特定の回答やテクニックの暗記を推奨するものではありません。
-
面接は、大学と受験生が互いの相性を確かめる双方向の対話です。自分の言葉で、誠実に、事実に基づいて語ることが最も大切です。
-
応募要項・評価観点・出願スケジュール等の最新情報は必ず公式の募集要項をご確認ください。
7. まとめ:面接は「学びのスタート」を共有する場
AO入試の面接は、「何を話せば得か」ではなく、大学で何を学び、どのように社会に関わりたいかを一緒に描く時間です。
-
経験を事実ベースで振り返り、そこから得た学びを言語化する。
-
大学の教育内容と自分の関心を結びつけ、将来像と往復させる。
-
当日は落ち着いて対話し、分からないことは確認しながら進める。
この準備プロセス自体が、入学後の学修やキャリア形成の土台になります。自分らしい言葉で、等身大の魅力を伝えてください。
【日本経済大学のキャンパスライフ】
日本経済大学は、単なる学問だけでなく、豊かなキャンパスライフを通じて学生たちの成長と個性の伸展を促進します。
キャンパス内では多彩なクラブやサークル、文化イベントが活発に展開され、学生たちは自分の興味や才能を発揮し、新たな交友関係を築くことができます。
学外活動も大いに奨励され、学生たちは都心の様々な文化やイベントに触れることができます。
これにより、卒業後には社会においても多様な価値観を理解し、柔軟な思考力を備えた人材として成長することが期待されます。
資格取得・奨励金給付制度を通じて、学生たちは自己成長に対する励ましを受け、自身の専門分野での深化を目指すサポートが充実しています。
この制度は、学業だけでなく、将来のキャリアにおいても大いに活かされることでしょう。
日本経済大学のキャンパスライフは、学問だけでなく、人間形成としての重要な役割を果たしています。
詳細は以下のホームページをご覧いただき、日本経済大学の魅力やキャンパスでの日々の活動に触れてみてください。
・日本経済大学HPホームページ
https://www.jue.ac.jp/
・日本経済大学 資格取得・奨励金給付制度
https://www.jue.ac.jp/qualification/
ぜひ、日本経済大学のキャンパスでの充実したライフスタイルをご体験ください。